【概要】
本記事では、さいたま新都心にある児童発達支援のサービスを展開している、以下3つの施設に関して詳しく紹介します。
- あさひ福祉サービス 児童デイサービス あさひ丸グループ
- ぶらいと
- TAKUMI
あさひ福祉サービス 児童デイサービス あさひ丸グループ

あさひ福祉サービス 児童デイサービス あさひ丸グループ公式サイトより引用
以下では、さいたま新都心にある児童発達支援サービスを展開している1箇所目の施設、あさひ福祉サービス 児童デイサービス あさひ丸グループについて紹介します。
あさひ丸グループとは?

あさひ丸グループとは、障害をもった子どもに児童発達支援や放課後等デイサービス事業所・児童デイサービスあさひ丸などの療育の場の提供を行っています。
この他にも働く場所として生活介護事業所「あさひ元気村」や、住む場所としてグループホーム「まるの家」などがあります。
さらに両親相談の場として相談支援事業所「あさひハートケア」、1対1の外出サポートとして移動支援事業所「あさひケアサービス」なども展開しています。
あさひ丸グループの児童発達支援&プログラム内容とは?

あさひ丸グループでは、児童発達支援として未就学児の発達に不安がある子供向けにサービスを展開しています。
展開しているプログラム内容は主に、日常訓練・音楽療法・療育全般を担っています。
サービス内容
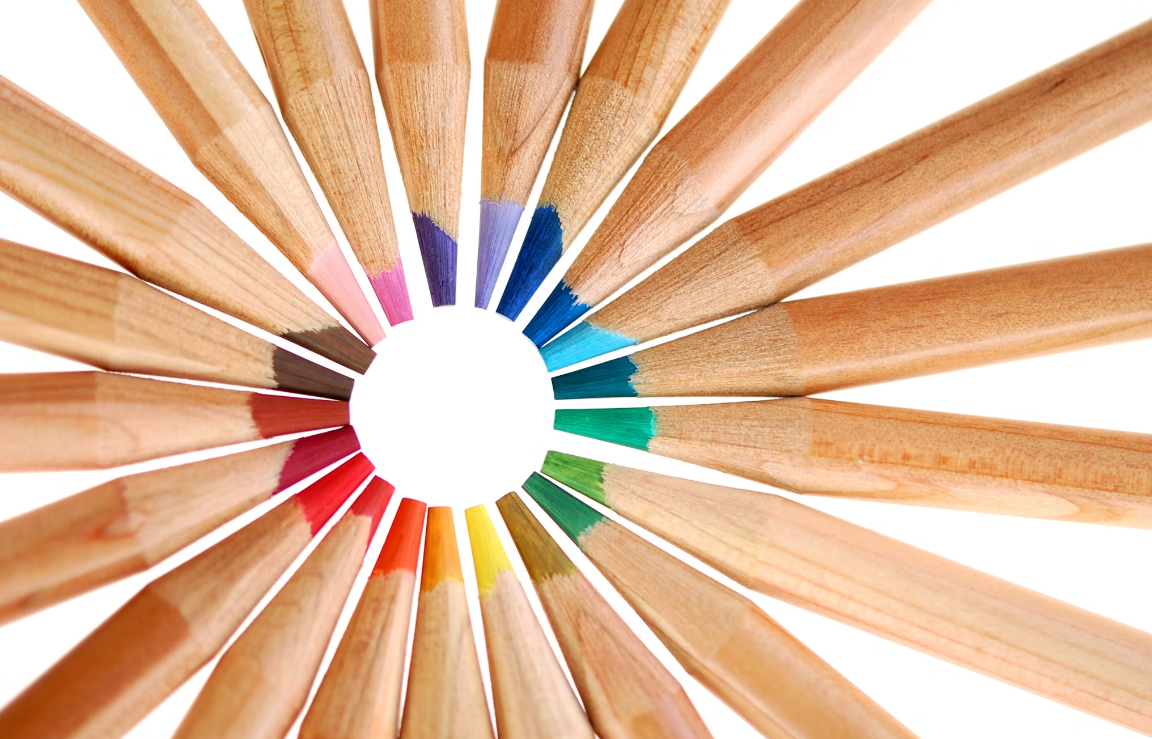
あさひ丸が提供しているサービス内容を、施設の設備や1日の過ごし方にフォーカスして見ていきましょう。
施設について
あさひ丸では以下9つの施設運営を行っています。
- 児童デイサービス あさひ丸
- 児童デイサービス あさひ丸戸田
- 児童デイサービス あさひ丸さくら
- 児童デイサービス あさひ丸ひろば
- 児童デイサービスあさひ丸ひろば第二
- 児童デイサービス あさひ丸リズム
- 児童デイサービス あさひ丸パーク
- 児童デイサービス あさひ丸新都心
- 児童デイサービスあさひ丸 宮原・土呂
1日の過ごし方
あさひ丸では平日と休日では1日の過ごし方が異なります。
以下では、平日と休日の過ごし方について時間別に詳しく紹介します。
平日
平日の過ごし方は以下の通りです。
13時半~16時
お迎え
自宅もしくは学校などに送迎車でお迎えに上がります。
教室到着後は荷物の整理や着替えを済ませ、連絡帳を提出してもらいます。
メディカルチェック・トイレ・水分補給・挨拶・基本的なルール・マナーなど習慣づけを大切にしています。
自身で行えることは積極的に取り組みを促しつつも、自身で行うのは困難であることに関してはスタッフがサポートします。
14時~16時
スタッフとコミュニケーションを取りつつ、自身が興味を持った遊び・活動などをスタッフや友達と共有することで楽しく過ごします。
この時間を利用して学校の宿題を終わらせる子どももいます。
16時~16時20分
おやつタイムとして皆でテーブルを囲み、おやつの時間を満喫しています。
16時20分~17時30分
活動テーマとレクリエーション・課題の取り組みなどを行う時間としています。
本時間の取り組み内容は、各事業所・設備環境・スタッフの人員配置・資格などで活動内容が異なります。
17時30分~18時
帰りの準備・帰りの会を行います。
その他の今日の振り返りや掃除手伝い・紙芝居・送迎順に整列するなど、ルールやマナーを遵守しながら帰る前に切り替えの時間を設けています。
18時~
送迎
自宅まで送迎車でお送りします。
送迎時も挨拶や基本的ルール・マナーなどを習慣化できるように取り組みを行っています。
休日
8時30分~9時30分
お迎え
自宅や学校などに送迎車でお迎えに上がります。
10時~10時20分
おやつタイム
友達とテーブルを囲み楽しくおやつを食べます。
手洗い・うがい・おやつ準備・片付け・歯磨きなどの一連の流れをスタッフがサポートしながら、一連の流れをスタッフがサポートしながら、生活習慣向上を目指します。
10時20分~12時
自身の意思を最大限尊重しつつ、活動テーマや集団レクリエーションへ参加可能な児童はスケジュールを組みます。
活動テーマや集団レクリエーションがない児童に関しては、個々に適した活動を取り入れ楽しい時間を過ごせるようにスタッフが工夫を凝らしています。
12時~13時
皆でテーブルを囲み、楽しく昼食を食べます。
13時~14時30分
自由課題
スタッフと密接にコミュニケーションを取りつつ、自身で興味がある遊びや活動を通し、スタッフ・友達と共有しながら楽しく過ごします。
14時30分~15時
帰り準備・帰りの会・掃除・お芝居・クールダウン・トイレなど一連の身支度を済ませます。
自身で行えない場合は、スタッフがサポートしながらゆくゆくは自分でできるようになるまでサポートします。
15時~
自宅まで送迎車でお送りします。
ぶらいと

以下では、さいたま新都心にある児童発達支援サービスを展開している2箇所目の施設、ぶらいとについて紹介します。
ぶらいとが伝えたいこと

自閉症スペクトラム障害などの発達障害を持っている子どもは、医師から診断を受けた後に、公的療育センターを初めて受診するのに数ヵ月時間を要する場合があります。
その後民間で運営している療育施設を訪れても、現状は定員オーバーで療育開始まで数年待機していなければならない場合もあります。
障害児の療育サポートする施設が圧倒的に不足している現代において、大切な子どもの時間をただ待機するだけでは埒が明かないと思い、ぶらいとでは療育活動をスタートさせました。
サービス内容

ぶらいとで提供しているサービス内容は以下が挙げられます。
- オーダーメイド療育
- ABA
- 独自のシステム
- 個別療育の流れ
以下で詳しく見ていきましょう。
オーダーメイド療育
通所している児童の成長や発達状況はさまざまです。
ぶらいとではオーダーメイド療育として、児童一人一人の状況把握や対応カリキュラムの作成を行っています。
オーダーメイド療育に対応するスタッフは、経験や専門性が豊富にあるスタッフで対応しています。
ABA
ABAは日本語に訳すと、応用行動分析と言われる療育システムです。
ABAを実施することで、児童一人一人の行動を分析単位で、見える行動ごとに判断・分析を行っています。
独自のシステム
独自システムの導入により図偉業風景を動画に収め、保護者へ情報共有を円滑に行っています。
保護者も施設での授業風景を確認できるため、安心して子どもの教育を一任することができますね。
個別療育の流れ
個別療育の流れは以下の通りです。
①アセスメント(現状把握)
アセスメント検査と保護者から子どもについて聞き取りを行います。
その上で、施設スタッフによって子どもの行動観察などを基本とし、現状把握を行います。
②個別支援計画の作成
アセスメントの結果を基に、子どもの発達課題に応じた個別支援計画を作成します。
計画は6か月痰飲で作成しつつも都度見直しを行い、計画内容のブラッシュアップに努めています。
③個別療育プログラムの実施
個別支援計画に沿った療育プログラムを実施します。
1コマ約45分程度を想定しています。
プログラムの実施を通し、子どもの発達状況を加味しながら、保護者と連携し個別療育プログラムを進めています。
④結果の評価・改善
日々の療育を通し子どもの発達状況を評価し、療育プログラムの改善を行います。
目安としては6か月単位で計画のブラッシュアップを実施しています。
療育システムについて

発達障害と一口で言っても自閉症やADHDなど、症状は千差万別です。
したがって医療で治療するのも常用ですが、療育によるサポートも重要です。
ぶらいとではABAを基本とした療育や、臨床美術に基づいた美術療法による療育を実施しています。
以下で詳しく見ていきましょう。
ABAを基本とした療育
ABA療育は、発達障害を持っている子どもの社会性や知能は改善見込みがあると考えられ、行動分析による行動の基本原理に基づき子どもの行動を変えて行きます。
行動分析は1930年のアメリカでB.F.スキナー博士により確立された行動科学で、人の行動はご褒美を与えることで変わることを立証しています。
ABAでは子どもでも理解しやすいタイミングでしっかり褒めて育てることを基本に、ぶらいとでもしっかり褒めて育てる姿勢は崩さず、常に子どもの行動を見守り柔軟な対応に努めています。
臨床美術に基づいた美術療法による療育
美術作品を見ると多くの人は心を動かされる感覚があるでしょう。
絵・オブジェなど美術作品を作ることで脳が活性化し、感情豊かになったり心が解放されたりするのを目指すのが臨床美術です。
臨床美術は右脳の活性化が社会性を向上させるといった医学的根拠があり、自閉症や認知症の症状も緩和させる力を秘めた優れた療法です。
ぶらいとでは臨床美術を広めるために、さまざまな活動を行ってる彩球と連携し、専門臨床美術士による独自のプログラムを実施しています。
療育カリキュラムについて

ぶらいとで実施している療育カリキュラムは以下の通りです。
- モンテッソーリ円柱さし
- 型はめ
- シーツ遊び
- 絵画制作「色彩と色感」
- オブジェ(立体)制作「かぼちゃの新聞工作」
以下で詳しく見ていきましょう。
モンテッソーリ円柱さし
モンテッソーリ円柱さしは、子どもの自己教育力を提唱したモンテッソーリの理念に沿って考案された教具です。
具体的な作業内容は、高さや太さが異なる円柱を同じ大きさの穴にはめ込む作業です。
形や大きさを理解する能力や指さしや言語によって提示に応じる力を養えます。
型はめ
型はめは、パズルピースの形を見分け同じ形の穴を探してはめ込む教具です。
型の理解・パターンを弁別する能力・指さしや言語に対応する能力を養えます。
シーツ遊び
シーツ遊びは、子どもひとりが乗ったシーツを大人2人で持ち上げ、ハンモックのようにシーツを動かす遊びで脳に心地よい刺激を与えることができます。
身体を動かすことでバランス感覚・柔軟性を向上でき基礎的運動能力が身につきます。
さらに順番を待つという規律性を身に着けられるため、社会性が培われます。
絵画制作「色彩と色感」
色彩と色感は、絵の具のパステル・色鉛筆・墨などさまざまな色と出会い、素材や画材の触感を楽しみつつ自由に描きます。
オブジェ(立体)制作「かぼちゃの新聞工作」
オブジェ(立体)制作「かぼちゃの新聞工作」は、本物のかぼちゃを診たり触れたりします。
前述で感じたことを基に新聞紙で形を作り色を塗って表現します。
他にも粘土・木材・石・針金などを用いて、さまざまな立体を作成しています。
TAKUMI

以下では、さいたま新都心にある児童発達支援サービスを展開している3箇所目の施設、TAKUMIについて紹介します。
TAKUMIについて

TAKUMIでは、運動と創作・学習を通じて、子どもへ笑顔と自信をモットーに、体幹・姿勢・ストレッチ・体操・運動のコツ・切り替え・集中力・手先訓練などを取り入れた、運動教育を提供しています。
さらに運動以外にも学校や社会で必要になる、ソーシャルスキルの習得も支援しています。
TAKUMIにおける学習支援

O-DANより引用
TAKUMIにおける学習支援は以下の2パターンがあります。
- 運動教育
- ソーシャルスキル
以下で詳しく見ていきましょう。
運動教育
運動教育では、体幹・姿勢・ストレッチ・体操・運動のコツ・切り替え・集中力・手先訓練を、取り入れた教育を展開しています。
施設利用時間内で楽しみつつ、苦手を段階的に改善することを常に考え、実施しています。
運動プログラムを中心に子どもの苦手を発見し、一方で子どもの得意を見つけ身体能力向上に努めています。
ソーシャルスキル
ソーシャルスキルでは、挨拶・返事・躾・マナーなどの習得を支援しています。
学校や社会で必要となるソーシャルスキルを学べることで、子どもが学校や社会にスムーズに馴染めるでしょう。
サービス内容

ここまで記事をご覧いただいている方の中には、TAKUMIではどのようなサービスを展開しているのか気になる方も多いでしょう。
以下ではTAKUMIがどのようなサービスを展開しているのか紹介します。
未就学児を対象として児童発達支援
TAKUMIでは0歳〜6歳の主に小学校入学前の子どもを対象に、運動プログラムを通して体幹・姿勢維持・運動のコツなどの、創作支援を実施しています。
前述以外にも小学校入学前に身に着けておきたい基礎的な力を養う支援を、子どもの一人一人に合わせてプログラムに沿って実施しています。
対象となる子ども
居住地の市区町村で受給者証を取得もしくは医師の意見書を持った、幼児・小学生以上の子どもが対象です。
さらに以下の項目に該当する子どもも対象となります。
- 運動が苦手または楽しく感じない
- 体を動かす場所や時間がない
- 放課後一人の時間を持て余している
- 字がうまく書けない・漢字が覚えられない
- 表が読めない
- 自分に自信がなく自己肯定感が低い
- コミュニケーション・集団活動が苦手
- 列に並ぶのが苦手・長時間座っていられない
1日の過ごし方
TAKUMIでは子どもの特性や年齢に合わせ、3名前後の個別クラスや6〜7名前後の小集団クラス単位でクラスを運営を行っています。
とある日のタイムスケジュールは以下の通りです。
14時~15時半 幼児少人数クラス(3人)
115時半~18時 小学生少人数クラス(3人)
前述のタイムスケジュールを参考にするとしっかり年齢別にクラスが区分けされ
少人数でのびのび学ぶことができますね。
TAKUMIが大切にしている想い

TAKUMIが大切にしている想いは、大きく分けて以下の2点が挙げられます。
- 子どもへ自信をつける
- 子どもへできる喜びを伝える
前述の内容を以下で詳しく解説します。
子どもへ自信をつける
TAKUMIでは子どもができないことでも、ゆっくり頑張れば少しずつできるようになることを、運動を通して子どもへ教えています。
子どもが本来持っている力を引き出し、眠っている力を引き出し可能性を狭めたくないと考えています。
子どもができないと思っていることをできるようにし、子ども自身が自信を持って日々を過ごしてほしいという想いを大切にしています。
子どもへできる喜びを伝える
レッスンを重ねることでできないこともできるようになり、家族も知らない子どもの一面を垣間見れるでしょう。
TAKUMIではできないことをできるようになる喜びを存分に感じ、未来に向かって大きく羽ばたいて欲しいと思っています。
参考記事
http://asahi-shougaishafukushi.com/
「ものづくり」を通じた新しい療育のカタチ|FabriCoのご紹介
モノを作る、モノを語る。個性を活かすものづくり療育
さいたま市内で学習支援型の放課後等デイサービスをお探しの保護者の皆様に、ぜひ知っていただきたいのが「FabriCo(ファブリコ)」です。
FabriCoは、従来の学習支援とは一味違った「ものづくり」をテーマにした放課後等デイサービス・児童発達支援施設です。単なる勉強の補習ではなく、ものづくり(Fabrication)を通して、自分や他者、社会への関心を育むことを目指した独自の療育を行っています。
今話題のSTEM教育×アナログものづくり
FabriCoでは、時代の最先端を行くデジタル技術と、昔ながらのアナログな手作業の両方を大切にしています:
デジタルなものづくり活動
- プログラミング教育
- ロボット制作
- STEM教育プログラム
- デジタル技術を活用した創作活動
アナログなものづくり活動
- 工作・クラフト活動
- 裁縫・手芸
- 料理・調理実習
- 伝統的な手工芸
FabriCoが大切にしている3つのポイント
1. 一人ひとりに合わせた個別〜小集団療育 お子さんの発達段階や特性に応じて、完全個別から小集団まで、最適な形態での療育を提供します。
2. 対話的な学びを重視 ものづくりを通した対話的な学びを大切にし、サークル対話や振り返り活動を通じて、自分自身について考える力を育てます。
3. 自分・他者・社会への関心を育む ものづくりという具体的な活動を通して、実感を持って「じぶんごと」として考える力を育成します。
じぶんごとラボとの連携で培われた実績
FabriCoを運営する一般社団法人こどもとみらい教育研究会では、学童保育「じぶんごとラボ」も運営しており、長年にわたって子どもたちの自己理解と成長をサポートしてきた豊富な実績があります。
この経験に「ものづくり」という要素を加えることで、より具体的で実感の持てる療育プログラムを実現しています。
所在地・お問い合わせ
FabriCo さいたま新都心
- 運営:一般社団法人こどもとみらい教育研究会
- 住所:埼玉県さいたま市南区別所5-15-2
- お問い合わせ:各施設のLINEから気軽にご相談ください
最適な放課後等デイサービス選びをサポート|こども相談支援Un-School計画
お子さんにぴったりの療育環境を見つけるお手伝い
「あすぽーと」「ソーシャルブレインズ」「ハッピーガーデン」「FabriCo」…さいたま市内には本当に多様な特色を持った放課後等デイサービスがあります。
でも、**「うちの子にはどこが一番合っているんだろう?」**と迷われる保護者の方も多いのではないでしょうか。
そんな時に頼りになるのが、「こども相談支援Un-School計画」です。
Un-School計画が提供する包括的サポート
1. 総合的なアセスメント
- お子さんの発達状況や特性の詳細な把握
- 学習面・生活面・社会性の総合的な評価
- 保護者の希望や家族の状況の確認
2. 最適な事業所マッチング
- 学習特化型(あすぽーと)
- 体幹・脳幹トレーニング重視(ソーシャルブレインズ)
- 個別療育中心(ハッピーガーデン)
- ものづくり療育(FabriCo)
それぞれの特色を踏まえ、お子さんに最も適した事業所をご提案します。
3. 利用開始から継続支援まで
- 見学・体験利用の段取りサポート
- 個別支援計画の作成・調整
- 複数事業所の併用プランの提案
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
「Un-School」に込めた想い
「Un-School」という名前には、従来の学校教育の枠組みにとらわれない、お子さん一人ひとりに最適な学びの形を見つけていこうという想いが込められています。
学習支援が必要なお子さんには学習特化型を 身体づくりが必要なお子さんには運動プログラム充実型を 創作活動を通じて成長したいお子さんにはものづくり型を
画一的な支援ではなく、その子らしい成長を実現するための最適な環境選びをお手伝いします。
こんな時にUn-School計画にご相談ください
- 「放課後等デイサービスがたくさんあって、どこを選べばいいかわからない」
- 「うちの子の特性に本当に合っているか不安」
- 「学習支援重視?運動重視?どちらがいいのかわからない」
- 「複数の事業所を組み合わせて利用したい」
- 「事業所を変更したいけれど、適切な移行方法がわからない」
地域のネットワークを活用した連携支援
Un-School計画では、さいたま市内の優良な放課後等デイサービス事業所との密接な連携ネットワークを構築しています。
各事業所の本当の特色や実際の療育内容を詳しく把握しているからこそ、表面的な情報だけでは分からない、お子さんにとって最適な選択をサポートできます。
お子さんの明るい未来のために
放課後等デイサービス選びは、お子さんの将来に大きく影響する重要な決断です。
一人で悩まず、専門的な視点からのアドバイスを受けてみませんか?
お子さんの個性を大切にしながら、その子らしい成長を実現できる最適な療育環境を、一緒に見つけていきましょう。
お問い合わせ・ご相談 こども相談支援Un-School計画 詳細情報:https://fabrico.fun/consultation/
さいたま市内の放課後等デイサービス選びでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。FabriCoをはじめとした地域の優良事業所の中から、お子さんに最適な療育環境をご提案いたします。
